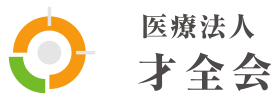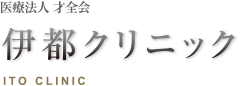![]()
- 甲状腺腫瘍、甲状腺癌、バセドウ病の外科的治療(手術前、手術後の診断と治療)
- 二次性副甲状腺機能亢進症など副甲状腺疾患の外科的治療
- 甲状腺・副甲状腺の内科的治療
- 腎臓病の診療
- 人工透析
・ウルトラピュアな透析液を始め、質の高い
血液透析療法
・バスキュラーアクセスの外科的診療
(造設術・修復術・PTAなど)
・フットケア
・栄養指導
・体力増進プログラム
(透析中の運動や家庭での運動指導)

診療時間
外来診療
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 09:30〜12:30 | 休診 | ○ | ※注1 | ○ | |||
| 10:30〜12:30 | ○ | |||||||
| 10:30〜13:00 | ○ | ○ | ||||||
| 午後 | 14:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ |
※外来診療は、初診・再診ともに予約制となっております。初診の方は事前に電話でご予約ください。
※注1 火曜日は予約検査及び手術の日となっており、一般外来診療は行っておりません。
人工透析
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15〜22:00 | 休診 | ○ | ○ | ○ | |||
| 08:15〜14:30 | ○ | ○ | ○ |
厚生労働大臣の定める掲示事項
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
【医療指定】
- 生活保護法指定医療機関
- 自立支援医療指定医療機関(更生医療)
- 身体障害者福祉法指定医療機関(じん臓)
九州厚生局長への届出事項について
以下の施設基準に適合している旨の届出を行っています。
(1)基本診療科の施設基準等
- 有床診療所入院基本料4
- 看護師配置加算1
- 夜間看護配置加算2
- 看護補助配置加算1
- 栄養管理実施加算
(2)特掲診療科の施設基準等
- 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1)
- 導入期加算1
- 透析液水質確保加算
- 慢性維持透析濾過加算
- ニコチン依存管理料
- 医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号に掲げる手術
<バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)> - 下肢末梢動脈疾患指導管理加算
当院は透析患者さんの下肢末梢動脈疾患重症化予防に取り組みます。
下肢の血流障害を適切に評価し、国立病院機構 九州医療センターと連携し、必要な方は早期治療を行います。全患者さんにABI検査(足の動脈硬化を測定する検査)と足のチェックを行います。
(3)その他
- 酸素の購入単価
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また公費負担医療の受給者で医療負担のない方についても明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですのでその点をご理解いただき、ご家族の方が会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にその旨お申し出ください。
保険外負担に関する事項
当院では以下の項目についてその使用に応じた実費の負担をお願いしています。
(1)日常生活上のサービスに係る費用
- 1.シャツ:880円/枚
- 2.ズボン:1,100円/枚
- 3.オムツ:220円/枚
- 4.貸出洋服クリーニング代:220円/枚
- 5.テレビ視聴料金:1,000円/月
(2)文書科
- 1.通院証明書:2,200円
- 2.診断書:2,750円
- 3.障害年金診断書:5,500円
- 4.診断書(生命保険):5,500円
(3)予防接種
- インフルエンザワクチン:4,000円※
※非課税対象(※以外は消費税を含んだ金額)
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は一切行っておりません。
医療情報取得加算
当院では、マイナンバーカードを健康保険証として使用できる体制を整えており、オンライン資格確認を行っております。オンライン資格確認により、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用することでより質の高い医療の提供に努めております。
一般名処方加算
当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに医療品の安定供給に向けた取り組み等を実施しています。
後発医薬品のある医薬品について特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
令和6年10月より医療上必要性がないにもかかわらず患者さんが長期収載品を選択した場合には、後発品との差額の4分の1を患者さんが負担する仕組み(選定医療)が導入されました。
一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
長期処方・リフィル処方せん
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して患者さんの同意に基づき療養計画を策定し、医師・看護師など他職種連携をして総合的な治療管理を行っています。
患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処方せんを発行すること、のいずれの対応も可能です。なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは症状に応じ担当医が判断いたします。